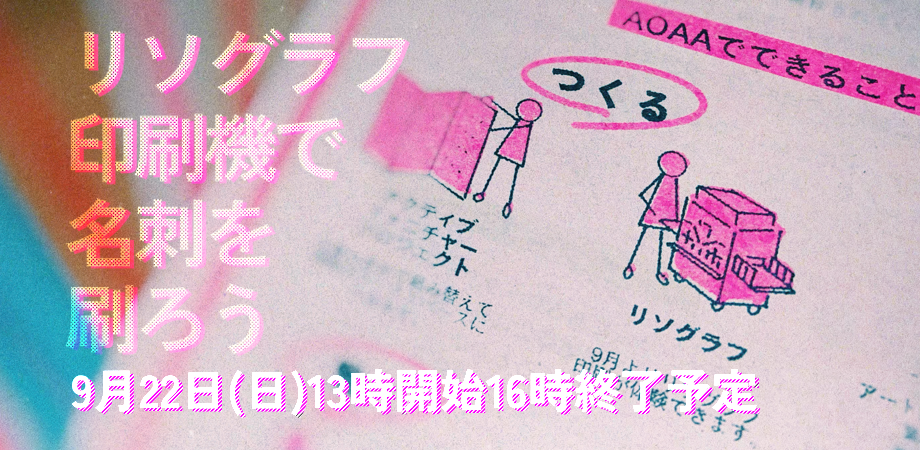プログラマーとしてコードを書きながら、10年以上コンテンポラリーダンスの舞台に立ち続ける女性がいる。彼女の言う「半歩越境」というスタイルは、決して二足のわらじではない。それは、スタートアップ大国イスラエルで目撃した、これからの時代を生き抜くための「働き方の最適解」だった。
過酷な修練、コンテンポラリーダンスの聖地イスラエルの芸術センター「スザンヌ・デラル・センター」での研修、そして京都府のアートプロジェクト参画へ。

――エンジニアとしての側面と、ダンサーとしての情熱的な側面。その原点はどこにあるのでしょうか?
「原点は高校時代のダンス部ですね。
正直、地獄でした(笑)。毎日『どうやって辞めようか』とばかり考えていたくらい、肉体的にも精神的にも追い込まれていました。
でも、全国大会レベルの景色を目の当たりにした時、理屈抜きで『美しい』と思ってしまったんです。『極限まで追い込まれた先にしか、生まれない表現がある』と知ってしまった。どれだけ苦しいプロセスでも、それを乗り越えて一つの形(アウトプット)に着地できた瞬間、それまでの苦労がすべて報われる感覚がありました。
これは今の仕事でも色んなものに通ずるものがあると思います。お客様から『ありがとう』と言われた時、『ああ、この瞬間のためにやってきたんだな』って、全ての苦労が喜びに変わる。
また当時の顧問の先生に言われた『今辞めたら腐るぞ』という強烈な言葉が、今もお守りのように私を支えてくれているのかもしれません(笑)」
イスラエルで出会った「スラッシュ・ワーカー」たち
――その後、渡った先がダンスとスタートアップの聖地、イスラエルですね。
「ええ。イスラエルの『Vertigo Dance Company』と『スザンヌ・デラル・センター』にてダンス三昧の日々を過ごしました。特に、そこで出会ったヤリン・リドール氏の影響は大きかったですね。
彼は音楽プロデューサーでありながら、環境保護活動家でもあり、クラブ経営者であり、テックの個人開発も行っていて、『あなたは何屋さん?』なんて質問が野暮に思えるほど、全てを本気で回してました。
――日本ではまだまだ珍しいスタイルですね。
「そうですね。イスラエルには、社会構造そのものに
『人は多面的である』という前提がある気がします。
例えば、彼らには『予備役(ミルイム)』という制度があり、普段はCEOやアーティストをしている人が、有事には一兵卒として現場に出ることも珍しくありません。
『一つの肩書きに固執しない』のではなく、
『複数の役割を持つことが、社会を生き抜くための基本OS』になっている。
日本では『二兎を追う者は…』なんて言われがちですが、彼らにとって複数の顔を持つことは、単なる趣味の延長ではなく、不確実な社会(地政学的にも)を生き抜くための『リスクヘッジ』であり、イノベーションの源泉という意識が徹底されているように感じました。」
――その「越境」スタイルが、帰国後の「京都府文化資源活用推進事業」で活かされたわけですね。
「そうですね!これは京都府が主導するアートフェスティバルで、府内全域に残る歴史的な文化資源、例えば古い寺院や自然の風景などを、デジタルアートや光の演出で書き換え、新しい観光資源として再生させるという大規模なプロジェクトです。
伝統という『最もアナログで重厚なもの』と、メディアアートという『最先端のデジタル技術』。この両極端なものを融合させる現場でした。」

――聞くだけで調整が難しそうな現場です。
「いえいえ、私はアシスタントとして末席にいただけですから。とにかく先輩方の背中を見て学ぶことの多い現場でした。
でも、その現場の空気を吸う中で、一つだけ大きな発見があったんです。
伝統や身体性といった『最もアナログなもの』が、デジタル技術によって翻訳・増幅されていくプロセスで、今まで『別世界の出来事』だと思っていたプログラミングと身体表現が、実は地続きにあるんじゃないか、と。
その時に感じた可能性が、今の私の越境というスタンスを支える根幹になっています。」
――今後の展望は
「今はプログラマーとして泥臭く手を動かしていますが、将来的にはやはり、自分のルーツである『芸術』と『デジタル』を結びつける事業を興したい。
その時、双方を知っていることは大きな武器になると思っています。
一度離れたからこそ、見える景色がある。いつか、イスラエルで見た彼らのように、文化とテクノロジーを軽やかに行き来するチームを作って、新しい価値を実装していきたいですね」